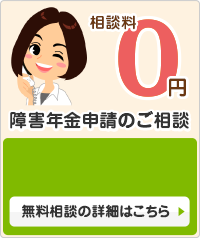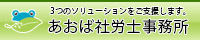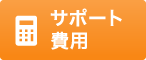うつ病 障害基礎年金2級:年額¥1,018,400(加算あり) 遡及額¥5,504,384
30代 女性 専業主婦 うつ病
1.相談に来られた状況
今から10年ほど前に気分の落ち込みがひどくなり、精神科を受診。
日常の些細なことに落ち込み、アルバイト先で少し注意されるだけで酷くショックに感じてしまったそうです。
現在まで長期にわたり通院を続け、服薬に頼って何とか生活をしてこられました。
しかし、うつ状態が強く、心も身体も常に辛く動けない状態が続いており、日中のほとんどの時間を横になって過ごしていました。
家事は満足にできない。子どもの面倒も見られない。
日常生活に著しい制限があるため、当センターへご相談に来られました。
2.経過
まずは、今から10年前の初診日の証明を取得するところから始めました。
当時の医院は廃院してなくなっていました。
現在も通院を続けている医院へカルテ開示を行い、前医の記録を見つけることができました。
続いて、ご本人へ日常生活で不便に感じていることを聞き取りしました。認定日は今から8年程前でしたが、状態はかなり悪く、日常生活に著しい制限があることを確認しました。
現在も悪い波がくると、動けず、一日中横臥して過ごさなければならない状態であることも確認しました。
問題は、医療機関での受診内容でした。
8年近く毎月受診していますが、診察時間は5分程度。医師との会話は、
医師「調子はどうですか」
相談者:「あまり変わりませ。」
医師:「じゃ、少し強いお薬出しておきますね」といった具合。
ほとんど外出ができず、お風呂にも入れず、横になって過ごしているのですが、診察の日だけは、気合をいれてシャワーを浴び、身支度を整えていきます。
しかし、とにかく辛いので、「すぐにでもこの場から立ち去りたい」という思いでいっぱい。
その結果、医師に十分に自分の障害状態を伝えることができなかったそうです。
障害認定日から現在まで同じ医院、同じ主治医にかかっておられたので直ぐに診断書依頼をしました。
ご本人様が医師に日常生活の障害状態をほとんど伝えることができていなかったので、私たちが真正の障害状態を正確にまとめ情報提供したうえで、診断書作成依頼しました。
しかし、できあがった診断書内容は、障害状態が全く記載されていませんでした。病院に行くときは身支度を整え、「いつもと変わりません」としか話していないのであれば、当然かもしれません。
早速、障害認定基準のスケールで再確認を依頼しましたが、医事課からは「再確認や修正はしません」との回答でした。
現在の状態が重く、障害認定基準に該当していても、直接証拠として証明するのは医師の診断書。
別の医院への転院もいかがですかと勧めつつ、診断書が真正な内容で記載して頂けるような補強書類がないか捜しました。すると、精神障害者手帳取得時の診断書が同じ病院で記載されていることがわかり、取得し内容を確認しました。やはり、ご本人様の障害状態とはかけ離れた障害状態が記載されていました。
もはや転院した方がいいだろう、と判断し診察が非常に丁寧で、実力のある医療機関をお勧めしました。
最後の受診の際に、ご本人から転院のため紹介状作成と、再度、当センター作成の認定基準に準拠したレポートを基に、医師に依頼をして頂くこととなりました。
すると後日、医事課より連絡があり診断書の再確認に応じるとのお話しでした。
認定日、現症ともに真正な障害状態が記載された診断書書いて頂くことができました。
申請書類を準備し、障害認定日(遡及)請求しました。
3.結果
障害基礎年金 障害認定日請求(遡及請求)が認められ2級 年額101万8400円(子の加算あり)、
遡及額 550万4384円が一括入金されました。
4.ポイント
いくら通院歴が長くても、きちんと医師に日常生活状態について話していなければ
真正な診断書はできあがりません。
社労士 齋藤の視点
 障害年金の受給率は近年下がり続けています。
障害年金の受給率は近年下がり続けています。
平成23年では、31.1%、受給者数230万人。
平成29年では、24.2%、受給者数207万人。
障害者数は増加しているのに、受給者数が減っている。認知度の低さ、制度瑕疵、医療機関関係者の識・知識の欠如……諸所の要因があるかと思います。
今回のケースでは、患者も医師に「伝える努力」をするべきであることがわかります。
現在は、情報格差が少なくなり、様々な媒体で医療情報を簡単に取得することができます。
つmsち患者側も、治療に参加する姿勢が求められると感じます。
医師による診断書は、診察を行い診療録(カルテ)作成する事が医師法第24条で定められています。
私たちは、障害年金を申請するにあったって、医療情報録(カルテ)を医療機関から取得して、内容を確認することが多くあります。しかし残念ながら、障害年金の診断書を作成できる内容、情報量のあるカルテはほとんどありません。
医師の診療行為を中心として、診療の時間軸にそって出来事・処置を記載している診療記録がほとんどです。
医師法施行規則第23条には診療録(カルテ)に記載する項目が定められています。
しかし、その中では、病気による症状の記載はあっても、患者の日常生活制限、労働制限など社会生活における障害状態の記載までは求められていません。
つまり、現在の多くの医療情報録(カルテ)は、医師目線での治療・診療録、保険請求用の診療録(メディカルレコード)となっています。
それに対して障害年金の診断書は、治療・医学的診断書ではなく、社会保障のための社会医学的な診断書です。つまり、社会生活においての障害状態を障害認定基準のスケールに則って、詳らかに記載する必要があります。
機能障害、能力障害、社会的障害(不利)の複層的な障害状態を記載しなければならないのです。しかし、現在の医師に、実社会での障害者の労働能力やエンプロイアビリティまで検討したうえで正確に診断書を作成することを求めること自体がナンセンスです。
なぜなら、医療機関は就職方式、雇用形態、給与形態、労働環境など、一般の労働市場と最もかけ離れた場所のひとつであるからです。
よって、医師に万能さや、すべてを求めることはお勧めしません。
患者はこの方々に、十分に話をかみ砕いて、わかりやすく説明し伝えることが必要なのです。
医者は、病気は見ても、患者の生活までは看てくれないからです。
そこまで求めないでください、彼らはスーパーマンではないのです。
自分は病気のため、特性上、人に上手く伝えることができない……
あきらめないでご相談ください。できる限りのサポートをします。
参考
医師法
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
医師法施行規則第23条
第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。
一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日
医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「うつ病精神疾患」の記事一覧
- 自閉スペクトラム症、多動症候群、うつ病 障害基礎年金2級:年額¥795,000
- 情緒不安症パーソナリティ障害、気分変調症 障害基礎年金2級:年額¥1,004,600(加算含む)
- 回避性パーソナリティ障害、他の特定される抑うつ障害 障害基礎年金2級:年額¥780,900
- 自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、うつ病 障害厚生年金3級:年額¥585,700(更新継続)
- 反復性うつ病性障害、注意欠如多動性症 障害厚生年金2級:年額¥1,780,804(加算あり)(更新継続)
- うつ病 障害厚生年金3級:年額¥586,300
- 反復性うつ病性障害 障害厚生年金2級:年額¥1,123,032
- うつ病 障害厚生年金2級:年額¥1,450,506
- 広汎性発達障害、うつ病 障害厚生年金2級:年額¥1,098,557
- 自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、うつ病 障害厚生年金3級:年額¥584,500
 反復性うつ病性障害 障害厚生年金2級:年額¥1,585,204(加算あり)
反復性うつ病性障害 障害厚生年金2級:年額¥1,585,204(加算あり)- うつ病 障害共済年金2級+遡及5年分
- 持続性気分障害 障害厚生年金3級:年額¥585,700
- うつ病 障害基礎年金2級:年額¥780,900
- うつ病 障害厚生年金3級:年額¥585,700