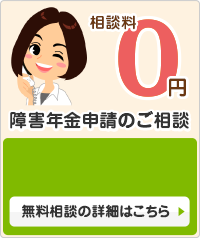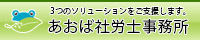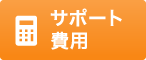事務所ポリシー
「本当に支援が必要な方に、必要な支援をお届けする。」
私たちは、専門家として障害のある方が、「人生の選択肢を、持ち活き活きと社会で共生できる」権利擁護を念頭に、相談サポートを行っています。
当センターでは、関係諸法令に精通した相談員が知識・経験をもとに相談を受けさせていただいております。
残念ながら、障害年金の受給率は非常に低く社会保障制度として十分に機能していないといわれております。(https://niigata-shogai.com/source)
厚労省、年金機構の不作為により認定基準改正やガイドライン改定未実施。不支給率の地域格差問題、不支給率の増加(令和7年)、粗雑な審査方法の放置(総合評価が粗雑)、不十分な不支給通知(医学的観点での説明がない粗雑な通知書)など瑕疵だらけの障害年金制度ではあります。
しかし瑕疵があろうとも、障害者の権利を守るためにセンター一丸となってご支援いたします。
ご自身で申請困難な方には、障害年金のエキスパート社労士事務所に連携いたします。
対策を行ったうえで申請を行う事を「申請ポリシー」としております。一件の申請に対して、要件確認、調査、ストーリー構成検討、医療機関対応、各種書類作成まご支援でおおよそ60時間程度をかけて申請支援しております。最近では、「発達障害」に強いとの評判を頂き、県外からの依頼希望が増加しております。 特に発達障害などの場合は、障害要件の証明が難しく100時間以上かかるケースも増えています事ご了解頂けますと幸いです。
「障害年金を受給すべき人、困窮されている方に、適正に受給していただく。」
ご相談内容についてはとても複雑なケースもあります。
そんな時、相談者にとって最善の方法を見つけ出し、解決を図ります。また医療者の視点で考える「障害」と法令で定める「障害」には違いがあります。
医療者や福祉関係の方々は、「治療によって、機能が回復して〇〇することが出来るようになった。」、「この訓練をすることによって、××出来るようになった。」といった機能回復や動作性改善といったベクトルで「障害」をとらえています。なぜなら、それが、医療者の仕事であり、医師の職業領域には社会保障(国民年金・厚生年金法における障害年金)は含まれていないからです。
詳しくは下記コラムをご覧ください。
しかし、障害年金に係る「障害」は、日常生活能力における障害状態を審査するものです。「機能回復」や「動作性改善」といった狭く、単純な状態を審査するものではありません。
法令で定める「障害」と医療者が考える「障害」の溝を埋める、橋渡しをしてゆきます。
通則法である、障害者基本法 第2条に国内法すべてに適用される「障害」の定義が定められています。国民年金法・厚生年金法で定める「障害年金」で審査される「障害」も同じ内容となります。つまり、家庭内での活動、地域コミュニティ活動、PTA活動、サークル活動、趣味の活動、ボランティア活動、経済活動、会社員としての活動、有償無償を問わず人を取り巻く一切の活動における制限を、社会の慣習、習慣、実社会での偏見、までも含めた障壁を「障害」と規定してます。
医師の書く診断書に「軽作業なら可能。」、「見守りがあれば軽易な労働可能」などの表記が散見されます。このような表記は障害年金用の診断書では意味が無い事になります。法令上の「障害」審査で求められているのは、実際の労働市場における就労機会や一般社会での稼得能力を審査するものであるからです。
このように、障害年金申請の現場では、法令上の「障害」を関係者に理解していただく事が最も重要な仕事であると考えております。このような専門家にしか分からない、年金請求実績に裏付けされた経験とノウハウを駆使し、相談者にとって法令で定める障害等級の年金がもらえるよう努力いたします。
もちろん、法令基準を理解された良いドクターと出会い、きちんと保険料納付がされており、証明すべき事項すべてが簡単に入手出来る場合もあります。このようなケースでは、本人申請でも私たち専門家の申請でも結果はあまり変わらないかもしれません。このような場合、私は①経済的に困っていない、②障害のある者を両親、兄弟、親戚が十分に養う能力がある この2点を満たした方は、専門家に依頼する必要がないとお話ししています。
当センターは、限られたマンパワー、リソースのなかで精いっぱいご支援を行っている状態です。年間ご支援できる件数は120件程です。発達障害など難しいご依頼が多くなり、ご希望に沿えない方、お待ちいただく方が出てしまうことご理解ください。